はじめに
LUMIX S9の一式を手放して小三元レンズセットと共にやってきたOM SYSTEMのOM-5 Mark IIですが、被写体認識AIが載っていないとか、エリアAFだと被写体がカメラ任せになっちゃう等といった不満点はあるものの、それを補っても余りある本体サイズのコンパクトさのお陰で、最近持ち歩くメインカメラとなっています。
ぶっちゃけ、購入する時には小型・軽量というポイントに極振り状態だったので、それ以外の部分に関しては「まぁいいか」って感じではあったんですよね・・・(;´Д`)
そもそもM4/3は手放して以降戻るつもりもそんなになかったので、OM-3に関してもヘリテージデザインなだけでそんなになぁ・・・って感じだったんですが、実際にOM-5IIを買ってから『自分の求めるものがOM-3の中にあった』という事実を後から知ってしまったわけです・・・(;´Д`)
で、色々と調べてみたりしたんですが、9月14日にマイクロフォーサーズ系の体験セミナーがあるので、そこでがっつり試してから決めようと思っていたんですけどもね・・・いや、もう遅かれ早かれだろうしということで思い切って買ってきてしまいました。
ザックリとした比較表
現状のOM SYSTEMのメインストリームとなっている3機種のザックリとした比較表を作ってみました。
表を見たら細かい違いがあったりもしますが、ホントにザックリと撮影に関する部分だけをまとめた感じになります。
動画はほぼ撮らないので割愛しています。
| OM-3 | OM-1 Mark II | OM-5 Mark II | |
| センサー | 4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー | ← | 4/3型 Live MOS センサー |
| 画素数 | 有効画素数 約2037万画素 総画素数 約2293万画素 | ← | 有効画素数 約2037万画素 総画素数 約2177万画素 |
| 記録媒体 | SDカード(UHS-II 1スロット) | SDカード(UHS-II 2スロット) | SDカード(UHS-II 1スロット) |
| ファインダー | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット | アイレベル式OLEDビューファインダー、約576万ドット | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
| 視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.23倍~約1.37倍 | 約100% / 約1.48倍~約1.65倍 | 約100% / 約1.23倍~約1.37倍 |
| ファインダー輝度調整/色温度調整 | 手動(輝度 ±7ステップ / 色温度 ±7ステップ 各GM, BA) | 自動調光機能、手動(輝度 ±7ステップ / 色温度 ±7ステップ 各GM, BA) | 自動調光機能、手動(輝度 ±2ステップ / 色温度 ±3ステップ) |
| AF検出輝度範囲 | 低輝度側(-5.5 EV) 高輝度側(19 EV) | ← | 低輝度側(-3.5 EV) 高輝度側(20 EV) |
| 測距点 / 測距点モード | クロスタイプ位相差AF(1,053点) コントラストAF(1,053点) Allターゲット Singleターゲット(1点) Smallターゲット(9点) Crossターゲット(39点) Middleターゲット(63点) Largeターゲット(165点) カスタムターゲット(点数、移動ステップ数設定) | ← | クロスタイプ位相差AF(121点) コントラストAF(121点) オールターゲット Singleターゲット(1点 標準) Singleターゲット(1点 スモール) Crossターゲット(5点) Middleターゲット(9点) Largeターゲット(25点) カスタムターゲット(点数、移動ステップ数設定) |
| AI被写体認識AF | 人物 / 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫) | ← | なし 顔優先AF/瞳優先AFのみ可能 |
| 撮影モード | P/A/S/M/B カスタム1~5 動画 | P/A/S/M/B カスタム1~4 動画 | P/A/S/M/B カスタム シーンセレクトAE アートフィルター 動画 |
| 感度(標準出力感度) | LOW(約80相当、100相当) 200 - 102400 | ← | LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600 |
| 連続撮影速度 | 〔連写〕: 約6コマ/秒 〔低振動連写〕: 約5.5コマ/秒 〔静音連写〕: 約20コマ/秒 〔静音連写SH1〕: 約120コマ/秒 〔静音連写SH2〕: 約50コマ/秒 〔プロキャプチャー〕: 約20コマ/秒 〔プロキャプチャーSH1〕: 約120コマ/秒 〔プロキャプチャーSH2〕: 約50コマ/秒 | 〔連写〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) 〔低振動連写〕: 約10コマ/秒 〔静音連写〕: 約20コマ/秒 〔静音連写SH1〕: 約120コマ/秒 〔静音連写SH2〕: 約50コマ/秒 〔プロキャプチャー〕: 約20コマ/秒 〔プロキャプチャー連写SH1〕: 約120コマ/秒 〔プロキャプチャー連写SH2〕: 約50コマ/秒 | 〔連写〕: 約6コマ/秒 〔低振動連写〕: 約5.5コマ/秒 〔静音連写〕: 約10コマ/秒 〔静音連写H〕: 約30コマ/秒 〔プロキャプチャー連写H〕: 約30コマ/秒 〔プロキャプチャー連写〕: 約10コマ/秒 |
| ピクチャーモード | i-Finish Vivid Natural Flat Portrait モノトーン カスタム 水中 カラークリエーター アートフィルター モノクロプロファイルコントロール カラープロファイルコントロール | i-Finish Vivid Natural Flat Portrait モノトーン カスタム 水中 カラークリエーター アートフィルター | i-Finish Vivid Natural Flat Portrait モノトーン カスタム eポートレート 水中 カラークリエーター アートフィルター |
| カラープロファイルコントロール | プリセット:COLOR1/COLOR2/COLOR3/COLOR4それぞれに設定を保存可 12色それぞれの彩度を-5 ~ +5 の11ステップで調整可 シェーディング効果: -5 ~ +5 の11ステップ設定可 (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) | ー | ー |
| モノクロプロファイルコントロール | プリセット:MONO1/MONO2/MONO3/MONO4それぞれに設定を保存可 カラーフィルター効果: 8色(赤/オレンジ/黄/黄緑/緑/シアン/青/マゼンタ)/3ステップの強度選択可/無し シェーディング効果: -5 ~ +5 の11ステップ設定可 粒状フィルム効果: 弱/中/強/Off 調色効果: セピア/青/紫/緑/無し (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) | ー | ー |
| ライブND | 可(ND2/4/8/16/32/64) | 可(ND2/4/8/16/32/64/128) | 可(ND2 / 4 / 8 / 16) |
| ライブGND | 可(ND2/4/8) | 可(ND2/4/8) | ー |
| 三脚ハイレゾショット | JPEG (80M) 10368 x 7776 JPEG(50M) 8160 x 6120 JPEG(25M) 5760 x 4320 RAW* 10368 x 7776 | JPEG (80M) 10368 x 7776 JPEG(50M) 8160 x 6120 JPEG(25M) 5760 x 4320 RAW* 10368 x 7776 | JPEG(50M) 8160×6120 JPEG(25M) 5760×4320 RAW 10368×7776 |
| バッテリー | リチウムイオン充電池 BLX-1 | ← | リチウムイオン充電池 BLS-50 |
| USB給電 | USB/PD規格デバイスより給電可能 | ← | USB給電可能 |
| 撮影可能コマ数 | 標準:約590枚 低消費電力撮影モード:約1040枚 | 標準:約500枚 低消費電力撮影モード:約1010枚 | 標準:310枚 低消費電力撮影モード:640枚 |
| 本体寸法 | 約139.3mm(W)x 88.9mm(H)x 45.8mm(D) | 約134.8mm(W)x 91.6mm(H)x 72.7mm(D) | 約125.3mm(W)× 85.2mm(H)× 52.0mm(D) |
| 重さ | 付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:496g 本体のみ:413g | 付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:599g 本体のみ:511g | 付属充電池およびメモ リーカード含む、アイカップなし:418g 本体のみ:370g |
| 実売価格 | ¥23,3410 | ¥27,5220 | ¥156,420 |
OM-3はOM-1 Mark IIをベースにして削れる部分をOM-5IIクラスまで落としてバランスを取った機種とも受け取れるスペックをしています。
EVFがOM-5IIクラスに落ちてますが、構図メインで考えるならそこまで高解像度なEVFも必要ないし、横幅が大きく広がる以外は大きなデメリットはないかなぁと・・・(グリップがないというのもありますけど・・・)

とはいえ、グリップまでつけると写真のように高くなって、横幅が指の厚みくらいの差が出るので一回り大きいカメラになった感じがします。
大きなメリットとしてはOM-1 IIと同じバッテリーになったことで標準使用でもOM-5 IIの倍近いバッテリーライフになっていますし、被写体検出AFやプロファイルコントロールを搭載しているので、まさに自分が欲しかったカメラがここに!といった感じ。
ただ、見ての通りOM-5 IIのコンパクトさは揺るがないので、嵩張らないカメラがいいならOM-5 IIかなぁと。
OM-3の開封と外観
パッケージはこの1ヶ月で見慣れてしまったクラフト紙っぽい箱のボックス。

側面には大きくキャッチフレーズが入ったOM-3の黒シールが貼られていました。
セット内容一式。

本体にバッテリー、ストラップ、Type-C to Cケーブル、写真には有ませんが簡易マニュアルと保証書が入っていました。
早速FalcamのMAGLINKを装着しました。

OLYMPUS PEN E-P7で見慣れたダイヤルが向かって左下に装備されています。
背面はOM-5 IIとは大きく変わっていないんですが、横に長くなった分だけボタンの間隔が開いています。

また、OM-5 IIではAF-ONボタンだったレバー部分がCPボタンに変わり、AF-ONは本体が広がってできたスペースに配置されています。
天面もそんなに変わらない・・・といいたいところなんですが、意外と変わっていて、左ダイヤルに撮影切り替えが集中することで右のモードダイヤルのカスタム登録がC5までに増えています。

一方、電源スイッチが左モードダイヤルとペンタ部分の間に配置されたことで、レバーがかなり短くなってしまったので電源スイッチのON/OFFが少しやりにくいかなぁと感じました。
カスタム可能であれば背面CPダイヤル部分のレバーに電源ON/OFFを割り振った方が片手操作がやりやすくなるのでいいかもしれませんね。
小型レンズがめっちゃ似合う
とりあえず、OM-3にパンケーキとまでは行かないけど、薄い単焦点レンズのM.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIを装着してみました。

なんていうか、いかにもカメラらしいカメラになりますね。
ちょっと斜めから見た状態でもコンパクトな単焦点レンズとは相性がいいのでめっちゃ似合います。

後述しますが持ちにくさはどうにもならないのでグリップを一緒に買ったんですが、見た目最優先だったらグリップの無いこのシンプルな状態が一番かっこいいと思います。
フードをつけてもそんなに嵩張らないので、マジで相性いいですね。

でもまぁ格好良さに極振りするのであれば、同じ17mm F1.8でも旧タイプの方が似合うと思います。
ただ、その場合は防滴なんかがなくなっちゃうというデメリットもありますけどね・・・
一緒に買ったもの
本体を買うのに合わせて一緒に買ったアイテムが以下のものになります
バッテリー&デュアルチャージャーセット『SBCX-1』
OM-3用のバッテリー『BLX-1』とデュアルバッテリーチャージャーの『BCX-1』がセットになったもの。

個別で買うよりも安いかな・・・よくわからんけど。
OM SYSTEMの公式オンラインショップだと会員登録してメルマガ登録とかをするとOM-3を買うのに10%OFFになるクーポンがもらえたり、3年間保証の他に9月15日までだとラッピングクロスとこのSBCX-1、OM-3関連アクセサリー20%OFFクーポン(9/30まで有効)も付いてきたりするので、場合によっては公式の方がお得な可能性もあります。
箱を開けるとBOX in BOX!ってやつで、それぞれが別にパッケージのまま入っていました。

こういったアイテムだけちょっと高級感というか高そうなパッケージなんですよね・・・
カメラだとまたこれの中に箱を作ったりする手間やコストが発生するからなんですかね?
チャージャーはType-C接続で2個同時に充電できるタイプ。
充電時間は2.5時間ということなので、1本に3.5時間掛かるOM-5IIよりも充電時間が早いです。
ぶっちゃけ、OM-5 IIはUSB給電ができるとはいえUSB PDに対応しているわけでは無いので充電時間がかなり掛かる感じになります。
なので、旅行先で3本充電しようと思ったら結構時間的な余裕がないと無理になるので、旅行に持って行くならOM-3の方がバッテリーライフも長いし充電時間も短いしで便利そうかなと思いました。

あと、バッテリーの方は端子カバーがついているとかそういったレベルの話ではなくて、カッチリとしたケースに入っていました。
簡単に開いてパカパカする感じでもないので持ち歩きに便利そうです。
Leofoto L字グリップ『LPO-OM-3』
流石にグリップ無しの状態だと12-45mmなんかは大丈夫でも、少し長い望遠ズームレンズになるとハンドリングが悪くなってしまうのでグリップも購入しました。
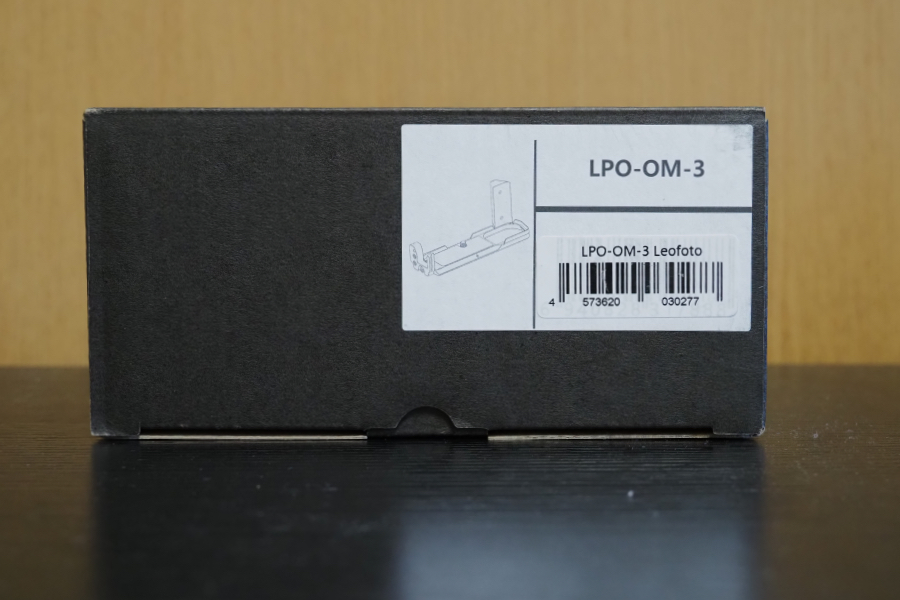
他社でも良かったんですが、このL字プレートだけサイドパーツが着脱できて縦アングルでも三脚に乗せられるので良かったんですよね。

価格的にも今のところ似たり寄ったりだったので、それなら三脚運用の時にでも使えるものにした方がいいかなと・・・
底面を撮り忘れていたので装着した状態で。

底面はこんな感じで装着したままでもバッテリーの着脱が可能。
プレート自体の着脱はLeofotoの文字が入った不等辺六角形の部分がマイナスドライバーになっているのでそれを使って取り外します。
よくあるマグネット固定になっているんですが、今まで使ってきたプレートだとマグネットが1つでポロポロ落としがちだったんですが、こいつはマグネットが3個になっていて3点止めになっていました。
形状的にも掬い上げるようなことをしないと外れないくらいの磁力があるので、よくある「いつの間にかなくなっていた」という可能性は少し軽減されている気がします。
これが縦位置固定用のプレート部分。

中央の固定しているネジの他に2本のピンがサイドプレートから出ているので変に回転したりと言ったことはありません。
三脚を持っていかないときは最初から外して持って行くということができるので、案外使いやすいかもしれません。
因みにですが、底面からの写真を見た時にフロント側のピクチャーダイヤルとグリップが近くて回しにくそうという感じがするかと思いますが、もともとピクチャーダイヤル自体が簡単に回らないようになっている(固い)ので、装着してなくてもカメラ正面からダイヤルを回す感じになるため付けてても外してても関係ありませんでしたw
まとめ
結局バッテリー充電からのスタートだったため、これを書いている時点ではようやく充電が終わりそうという感じになってきたところなので、細かいところや使ってみての感想はまた後日という形になります。
しかし、どうせ遅かれ早かれ買うからいいやと思ってたので思い切ってしまったわけですが、まさかの支払い金額がカードの分割枠を超えていたので1回払いという事になってしまい、どう考えても枠が回復しないのでキャッシングで支払うしかないという悪夢のような状況になってしまったわけですが、後悔はしてません。
・・・・もうやっちまったもんは仕方ないしw
頑張って働いて返していこう(;´Д`A


