はじめに
公開順序がどちらが先かまだ書いている時点では決めていませんが、SONY α6700レンズキットや数本のレンズを下取りに出してFE 16mm F1.8 GとFE 24-50mm F2.8 Gの2本を購入しました。
この2本を購入した理由はひとえに『α7CRが良すぎた』為に、『もっとフルサイズのレンズを使って撮りたい』と思った事が原因です。
α6700と同じAPS-Cの2600万画素でも十分だと思っていましたが、やっぱり6000万画素はえぐいッス。
という事で、色々考えた末に上記の2本にしたわけですが、レンズを選ぶ時に紆余曲折はあったので、これからフルサイズの標準ズームを買おうと思っている人の参考になるかは分かりませんが、なぜFE 24-50mm F2.8 Gにしたのか等を書いていきたいと思います。
最後に残った選択肢はFE 20-70mm F4 Gと24-50mm F2.8 Gの2本
下取りに出した機種は上の記事で書いているんですが、標準ズームの選択肢としては当初はシグマやタムロンなんかも考えてはいました。
流石にI型とはいえ24-70mm F2.8 GMは高価ですしね。
ただ、24-70mmのF2.8ってEマウントに限らず軒並み大きくて重いんですよ。
ぶっちゃけ機材が重いから本体を軽くしてるのに、それを出してるメーカーが重くて重いレンズばかり出すのはアレじゃね?って感じなんですが、メーカー的には色々あるんだろうね・・・
地味に28mmスタートだともう少し広くと思う場面もあったりするので、広角側は広い方がいいかなぁ・・・という事で、価格的に見たらそこまで大きな差が無いFE 24-50mm F2.8 GとFE 20-70mm F4 Gの2本から選ぶ事にしました。
価格的にはサードパーティーの28-70mmや28-75mm F2.8に比べると「高すぎる」という話もあるかとは思うんですが、F2.8通しの24mmスタートなのは大きなポイントになりますからね。
あと、大体普通のレンズだとテレ端になるほどレンズが伸びる形になりますが、この24-50mmに関しては50mmの時が一番レンズが短い形になります。
街中のスナップなんかに限らず、テレ端側ってよく使う事になるのでレンズの長さが一番短い状態で済む=電源を入れるだけで撮れるという形になるので、使い勝手がかなりいいんじゃないかなと思ったのもあったりします。
FE 24-50mm F2.8 Gのスペックと比較
FE 24-50mm F2.8 Gの基本スペックを記載するとともに、FE 20-70mm F4 Gのスペックも記載しておきます。
| FE 24-50mm F2.8 G | FE 20-70mm F4 G | |
| 焦点距離 | 24-50mm(APS-Cで36-75mm) | 20-70mm(APS-Cで30-105mm) |
| レンズ構成 | 13群16枚 | 13群16枚 |
| 開放絞り | F2.8 | F4 |
| 最小絞り | F22 | F22 |
| 絞り羽根 | 11枚 | 9枚 |
| 最短撮影距離(m) | 0.19(W)-0.30(T)(AF) 0.18(W)-0.29(T)(MF) | 0.3(W)-0.25(T)(AF) 0.25(MF) |
| 最大撮影倍率(倍) | 0.30(AF) 0.33(MF) | 0.39 |
| フィルター径 | 67mm | 72mm |
| レンズ内手ブレ補正 | 非搭載 | 非搭載 |
| 防塵防滴 | ○ | ○ |
| 最大径x長さ(mm) | 74.8x92.3 | 78.7x99 |
| 重さ | 約440g | 約488g |
焦点距離の幅とサイズ感を考えたら20-70mmを購入する方が使い勝手がいいとは思います。
接写性能にしてもテレ端の70mm時に25cmまで寄れますし、実際に自分もかなり悩みました。
購入するレンズが1本だけだったのであれば、20-70mmの方を選んでいたんじゃないかと思います。
ただ、もう一本FE 16mm F1.8 Gを買う事にしたのでスタートが20mmじゃなくて24mmでもいいかと思った事と、F2.8通しの明るさがよかったのでこのFE 24-50mm F2.8 Gを選びました。
一応、フルサイズのキットレンズにもなっているFE 28-60mm F4-5.6も「とりあえず」なレンズで買おうかなぁと思っていたんですが、沈胴時は45mmの長さですが、撮影時65mmくらいになるのと沈胴解除が手動&意外と力がいるので面倒臭い=鞄に入れる以外は沈胴解除のままという感じになるのかなと思ったら、4mm広角になるし2.7cmの差くらいは別にいいかと思ってFE 24-50mmだけでいいかなと。
どうしても手軽にしたかったらE 16-50mm F3.5-5.6 OSS IIを付けてAPS-Cモードでいいかなと思ってます。
こっちなら電源ONで自動的に沈胴解除だしね。
実はガッツリと被ってるSIGMA 18-50mm F2.8 DC DN|C
今まではα6700だったのでF2.8通しのレンズとしてはSIGMAの18-50mm F2.8 DC DN|Contemporaryを使用していました。
フルサイズ換算すれば27-75mmになるので28-70mmや28-75mmであれば今まで通りではあるんですが、やっぱりワイド側がもう少しというのがあったんですよね。
それを考慮すれば24-50mmのフルサイズと50-75mmのAPS-Cクロップが使える事になるので、SIGMAの18-50mmよりも使い勝手がよくなるわけです。
そう考えるとほぼ丸被りになってしまうので、実はSIGMAの18-50mm F2.8 DC DNも下取りに出そうかと思ったんですが、ETZ21 Proを使ってニコンのZマウントで使用している絡みもあって残しておく事にしました。
Zマウント用では代用できるレンズは存在していませんし、仮にニコン純正で出ても価格が高いでしょうしね。
FE 24-50mm F2.8 Gの外観
パッケージはいつもの感じのオレンジ箱でした。
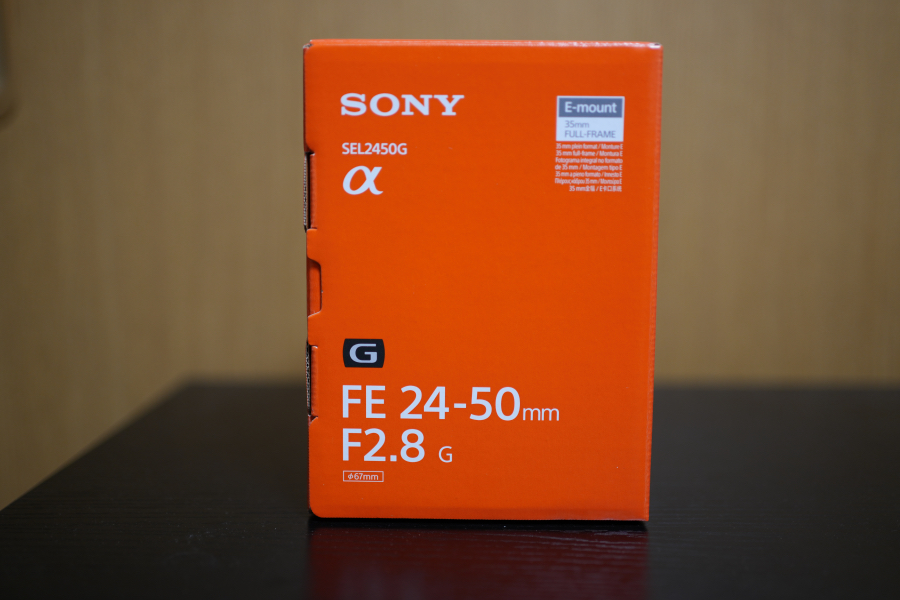
いつか1本くらいは正面が黒い箱のGマスターレンズを買ってみたいもんですな。
インナーフォーカスタイプのレンズではなく普通に伸縮するタイプのズームレンズではあるんですが、写真のようにテレ端になる50mmが一番レンズが短い状態になります。

通常はワイド端が一番短かったりするんですが、逆にこの状態なのがめっちゃ便利だなと思いました。
大体外でスナップをする時って35~50mmあたりを使うことが多いので、一番短いのはマジで楽。
後述しますが50mm時にはSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNと長さが逆転します。
一番前にフォーカスリング、中部左側にカスタム可能なフォーカスホールドボタン、AF/MF切り替えスイッチがあります。

その後ろにズームリング、絞りリングという順番になっています。
反対側には絞りリングのクリックON/OFFスイッチがあり、動画撮影時にクリックを無くすことで絞りを変えた時に音を拾わなくて済むようになります。

とりあえず、絞りリングがあると絞り固定で歩きながら撮影というのがやりやすくなるのでちょっと嬉しいですね。
他のレンズとの大きさの比較
左から一緒に買ったFE 16mm F1.8 G、APS-C用のSIGMA 18-50mm F2.8 DC DN|Contemporary、FE 24-50mm F2.8 Gです。

FE 16mm F1.8 GとSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNが同じくらいのサイズ。
FE 24-50mm F2.8 Gがそれよりも少し長いという感じになっています。
両方とも明るいレンズなので少し径が太くなっていますが、普通にコンパクトなので一緒に持ち出しても苦にならないですね。

この2本だと絞りリングの位置がちょっと異なるのでどっちかに統一とか出来んのかなぁ・・・
全然ピント合ってなかった(´・ω・`)
上で書いていたようにSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNとFE 24-50mm F2.8 Gのテレ端を比べると、少しだけFE 24-50mmの方が短くなります。

まぁ大差はないですが・・・
2本の最長状態がこちら。

18-50mm DC DNでは50mm状態が多かったので、風景なんかを撮る24mmはたまに使う感じだと考えたら24-50mmのテレ端が最短というのが使いやすいなと思いますね。
α7CRにFE 24-50mm F2.8 Gを付けてみた
フードなしで普通につけた状態。

レンズが最短の長さになる50mmです。
そして35mmがこちら。

ほんの少し繰り出すだけなので、この辺りのよく使う焦点距離だけだったらほぼズームしても長さが変わらない感じです。
そしてワイド端の24mm。

ワイドになるほど長くなっていきます。
フードを付けるとこんな感じ。

レンズのサイズからするとフードもコンパクトに感じます。
上の写真のように素の状態でも持ち歩くのには全く問題ない感じなんですが、やっぱりGP-X2がある方がしっくりきますね。

今時のミラーレス用レンズとして考えるとコンパクトなレンズではあるんですが、写真のようにα7CRのようなコンパクトボディにつけると、それでも大きく感じるんですよね・・・
マウント径と同じくらいのレンズの最大径=SIGMA 18-50mm F2.8 DC DNくらいのフルサイズ用レンズが出てきてくれたら嬉しいんですけどね。
とりあえずの試し撮り
24mmのワイド端でこれ。

レンズの基本スペックに書かれているレンズの長さというのはレンズの最短状態の長さを表記しています。
なので、沈胴レンズなら沈胴状態の長さだったりするので、実際に使う時には思ったほど小さくなかったりするわけですが、このレンズだと上で書いたようにワイド端が最短撮影距離の19cmとなっています。
50mm時には最短撮影距離が30cmなので、レンズ先端から被写体までのワーキングディスタンスは約19cmということになるんですが、このレンズは通常とは逆で24mm字が一番伸びる形になるので、フードをつけた状態で写真を撮るとフードの影がガッツリと写る状態になりました。
なので、上の写真はフードを外して最短あたりで撮影しています。
一方の50mmだとこんな感じ。

最短撮影距離が30cmってのは今まで使っていたSIGMA 18-50mm F2.8 DC DNと同じなので、そのままAPS-Cクロップしてやれば今まで通りというね・・・マジで便利なカメラですな・・・というか、マジでZマウントのAPS-Cで使うという事がなければ、18-50mm F2.8 DC DNの立場がなくなってしまった(;´Д`A
シグマがZマウントで18-50mm DC DNを出してくれたらマウント交換依頼出すんだけどなぁ・・・
まとめ
めっちゃお気に入りだったα6700ですが、α7CRがα6700も兼ねてくれるという事もあって、他のレンズと共に下取りに出して買い替えという形になりましたが、FE 16mm F1.8にしてもFE 24-50mm F2.8にしても実用性が高くて可搬性も高いのでα7CRとの組み合わせはとてもいいと思いました。
差額も2本で¥5,000くらいの追い金だけだったんですが、FE 16mm F1.8 Gの方はマップカメラのKenko ZXII プロテクタープレゼント対象になっていたので、ZXIIの販売価格を考えたらちょっと得してるまであったりします。

一応ZXIIはFE 16mmの方じゃなくて、普段使いにするFE 24-50mmの方に付けたんですけどね。
なんか普段使いのカメラがどんどん増えていってレンズも迷走気味になってますが、まぁそれも趣味かなと。
また今度持ち出して色々と撮ってみたいなぁと思います。



